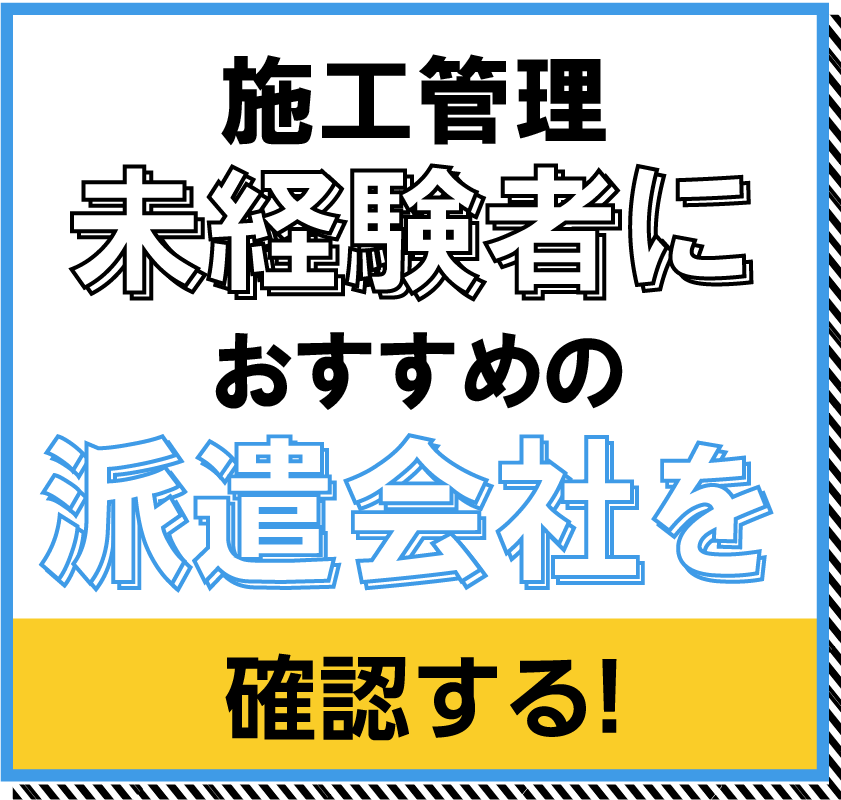技士補とはどのような資格?
目指すキャリア別!
施工管理技士の
派遣会社3選
施工管理技士としてのキャリア形成は、単に現場でのスキルを磨くだけではありません。豊富なキャリアの選択肢や専門性の追求、さらには海外での活躍を目指すことも可能です。しかし、どの派遣会社を選ぶかによって、その道が大きく左右されることも事実です。
「多様なプロジェクトを経験してキャリアを広げたい」「専門領域に特化してスキルを深めたい」「海外でチャレンジしてグローバルな視点を養いたい」— それぞれのキャリアニーズに応える派遣会社を厳選してご紹介します。
豊富な選択肢から
自分に合う工種を見出したい
コンストラクション

引用元:オープンアップコンストラクション公式HP
https://openupconstruction.co.jp/contact//
派遣できる工種
建築・土木・電気・プラント
資格支援内容
- 案件の領域バランスが良く、幅広い仕事のマッチングが可能
- 資格取得のサポートがあるので、経験を積みながら手に職を付けることができる
土木の分野で専門性を深めて
キャリア形成をしたい

引用元:カワノ公式HP
https://kawanogroup.com/
派遣できる工種
土木
特徴
- 大手ゼネコン直取引で土木建設業・工事に特化しているため、土木分野のスキルを活かして大型案件にも携われる
- 職場を紹介してくれるので、転勤など働く場所を変えたくない方におすすめ
海外勤務を視野に入れた
経験を積みたい

引用元:レガリス公式HP
https://regalis-gp.com/lp/
派遣できる工種
建築・土木・電気
特徴
- 政府開発援助を含む、海外案件の派遣実績あり
- 電話面接や面接同行のサポートがあるので、面接の成功率を上げたい方におすすめ
技士補とは
「技士補」とは、施工管理技士の資格試験で不合格になった場合でも、学科試験に合格していれば付与される資格であり、施工管理技士の「補佐」としての役割を担うことが可能になります。これまで、施工管理技士の資格を取得するためには「学科試験」と「実地試験」の両方に合格する必要がありました。しかし、2021年4月1日から、第一次検定に合格した者は技士補の資格が取得可能に。これまでは、監理技術者となった技術者が専任で配置されなければならなかった現場でも、主任技術者の資格を有する者と技士補の配置を要件に、監理技術者が複数の現場を兼任することが可能になったのです。
これは、従来の試験制度や監理者の配置に関して変更が加えられた結果となります。この変更に伴って、以前は「学科試験」と「実地試験」と呼ばれていたものが、「第一次検定」「第二次検定」と名称の変更も行われています。
新しくなった試験制度では、第一次検定に合格すると技士補の資格を与えられ、第二次検定を合格すると施工管理技士の資格を取得できるようになります。
また、受験資格の条件にも変更が施されており、一次検定の合格はこれまでの翌年までの期限ではありません。一度取得すると無期限の合格となるため、二次検定に挑戦して合格すれば、そのまま施工管理技士の資格を取得できるようになりました。また、2級の二次検定に合格すると、1級の一次検定を受験できるようになり、施工管理技士を目指すうえでの試験の流れがスムーズになりました。次の試験に向けてより集中して準備することができるようになったので、受験者にとって大きなメリットがある制度変更だと言えるでしょう。
「新・担い手三法」とは?
担い手三法によって、人手不足が顕著な建設業界で効率よく仕事を行い、また労働者の処遇の改善が期待されていました。これには一定の成果があったものの、さらに充実した環境改善を目的として、「新・担い手三法」が可決されています。
「担い手三法」により一定の成果があった
建設業界では、常々人手不足が問題となっていました。建設業界で働いている年齢層が高くなっており、高齢化によって定年から引退する人が今後増えていくことが予測されます。若手の育成もなかなか進んでおらず、人手は減少していく一方となっています。
そこで、労働者の待遇の向上や効率よく仕事を進められる取り組みが必要となり、「担い手三法」が規定されました。2014年に公共工事品確法と建設業法、また入契法を改正し、価格が適正に設定されることで、建設業の担い手の中長期的な育成や確保に必要な措置が行われたのです。
「新・担い手三法」で更なる成果を期待
その後、2019年に可決された「新・担い手三法」では、これまでの成果を活かして自然災害への対応や生産性向上の取り組みが盛り込まれています。
例えば、働き方改革の面では、適正な工期の設定や請負代金での下請け契約締結などが含まれています。また、社会保険加入の許可要件化も含まれているのが特徴です。長時間労働を是正して、処遇を改善するための内容も含まれることとなりました。
災害が発生したときは、緊急対応として契約と入札の仕組みを整え、地方公共団体と連携することも盛り込まれています。迅速に対応を行い、発注者との連携を図るための体制が整備されたのです。
また、経営業務管理責任者の基準が見直されたことで、事業環境が確保されました。建設業者が事業継承を行える仕組みも構築されています。
新・担い手三法では、担い手三法の実施によってどのような成果と課題があったのかを割り出し、さらなる成果を出すことが期待されています。災害が起きた際は守り手として需要な役割を占める建設業は、加速する人口減少を考慮して労働環境の整備に力を入れているのです。
建設業界はどう変わる?
新・担い手三法や技士補が新設されたことにより、若手が活躍できる機会が増強されたことや、下請け企業が現場に参加しやすくなったというメリットがあります。
若手の活躍の機会の増加
監理技術者は現場での作業が完了したあと、デスクワークが必要になっていました。監理技術者の数が不足していたのにも関わらず、負担は増えていく一方だった課題があったのです。法改正によって配置要件の緩和が行われたことで、技士補が監理技術者の補佐として業務を行えるようになりました。資格の有無で対応できる業務の制限がありましたが、技士補の導入によって監理者の負担は軽減。より多くの若い人材が活躍できる環境が構築されたのです。
下請け企業にもメリットがある
下請け業者にとっては、一次下請けの会社に指導監督の経験がある者を配置すると、二次下請けの会社では主任技術者の配置が不要となりました。
一定の条件を満たせば、専任の主任技術者が用意できない二次下請けの会社でも現場に参加できるようになり、元請けと下請けの会社の双方にメリットがあると言えます。
まとめ
建設業界では人手不足が大きな懸念点となってきました。技士補が新設されたことで、若手の活躍の場が広がり、監理技術者の負担が軽減されることが期待されます。また、改正によって、高校在学中に2級技士補の資格を取得できるようになり、より若い人材が建設業界で活躍するチャンスが増えてきました。建設業界で有資格者として働くには、受験資格の厳しい条件などが障壁となっている一面があったのですが、このたびの改正によって、それらの問題も少しずつ解消へと向かっていくことが期待されます。