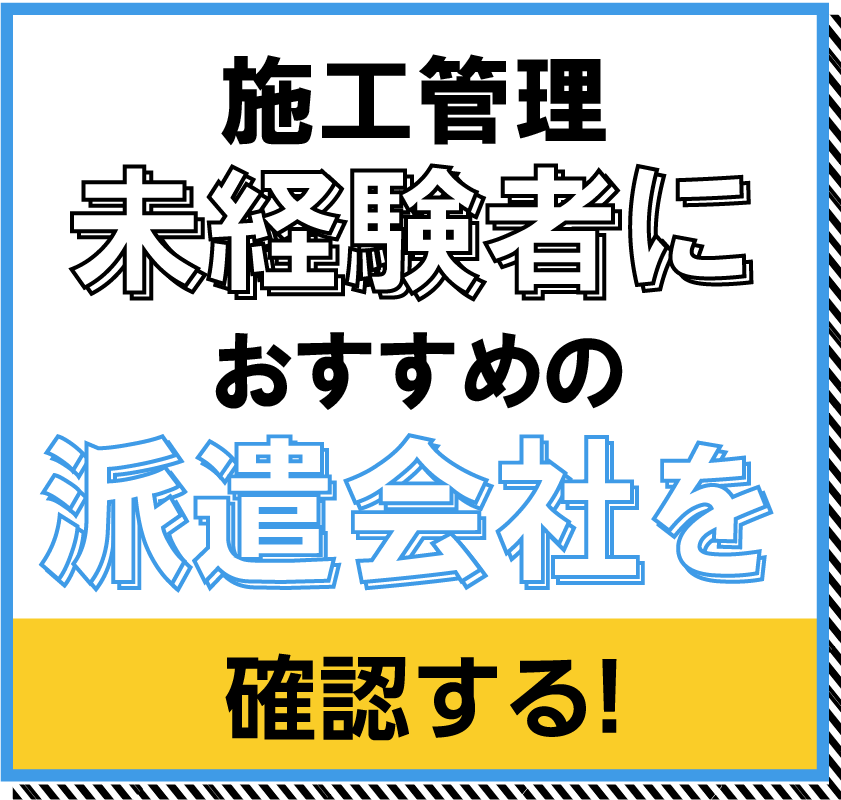基礎工事とは
目指すキャリア別!
施工管理技士の
派遣会社3選
施工管理技士としてのキャリア形成は、単に現場でのスキルを磨くだけではありません。豊富なキャリアの選択肢や専門性の追求、さらには海外での活躍を目指すことも可能です。しかし、どの派遣会社を選ぶかによって、その道が大きく左右されることも事実です。
「多様なプロジェクトを経験してキャリアを広げたい」「専門領域に特化してスキルを深めたい」「海外でチャレンジしてグローバルな視点を養いたい」— それぞれのキャリアニーズに応える派遣会社を厳選してご紹介します。
豊富な選択肢から
自分に合う工種を見出したい
コンストラクション

引用元:オープンアップコンストラクション公式HP
https://openupconstruction.co.jp/contact//
派遣できる工種
建築・土木・電気・プラント
資格支援内容
- 案件の領域バランスが良く、幅広い仕事のマッチングが可能
- 資格取得のサポートがあるので、経験を積みながら手に職を付けることができる
土木の分野で専門性を深めて
キャリア形成をしたい

引用元:カワノ公式HP
https://kawanogroup.com/
派遣できる工種
土木
特徴
- 大手ゼネコン直取引で土木建設業・工事に特化しているため、土木分野のスキルを活かして大型案件にも携われる
- 職場を紹介してくれるので、転勤など働く場所を変えたくない方におすすめ
海外勤務を視野に入れた
経験を積みたい

引用元:レガリス公式HP
https://regalis-gp.com/lp/
派遣できる工種
建築・土木・電気
特徴
- 政府開発援助を含む、海外案件の派遣実績あり
- 電話面接や面接同行のサポートがあるので、面接の成功率を上げたい方におすすめ
ここでは、基礎工事の種類や使用されるさまざまな工法、そして各工法の特徴などを解説しています。
基礎工事とは
基礎工事は、建物づくりにおいて何よりも重要な部分である「土台づくり」のための工事です。
基礎工事の種類
基礎工事には、大きく分けて2種類の工事があります。ひとつは「杭基礎」、そしてもうひとつは「直接基礎」です。前者の杭基礎には「既成杭工法」「場所打ち杭工法」の2つの工法があります。なお、直接基礎の工事は、さらに「独立基礎」「ベタ基礎」「布基礎」の3つに分類されます。これらの工法や工事について、ひとつずつ特徴や方法を見ていきましょう。
杭基礎
杭基礎は、軟弱な地盤に採用されることの多い工事です。地盤に充分な硬さがないと、建物の荷重が軟弱な地盤にそのままかかってしまうため、安定性に問題があります。そこで、数メートルの深さの硬い地盤部分に達するように杭を打ち込む杭基礎を採用するわけです。そうすることで、建物の基礎部分の安定性をアップすることができます。
また、この杭基礎によって、地震が発生した場合の液状化現象を防ぎやすくなるとされています。杭基礎のふたつの工法は次のとおりです。
既製杭工法
工場などで製造された、いわゆる既製品の杭を打ち込み、地盤を固めていきます。杭を沈設する際に、パイルドライバーやオーガマシンといった装置を使用します。
場所打ち杭工法
場所打ち杭は、現場の地盤に穴を掘り、その中に鉄筋を挿入し、そこにコンクリートを流し込むことで杭をつくる工法です。場所打ち杭工法の代表的な工法として挙げられるのが、「スーパートップ工法」と呼ばれるものです。これは、全周回転掘削機を使用して鋼管をつかみ、回転させて地盤の中に押し込んでいく工法になります。造成した掘削孔に鉄筋カゴを挿入すれば、杭を形成することができます。
直接基礎
直接工事は、ダイレクトに地盤に基礎をつくる基礎工事のことです。杭などの道具を使わずに基礎をつくるという点が、杭基礎の工事との大きな違いとなります。 杭を使用しないわけですから、地盤がやわらかい場合には適さない工事です。直接基礎が採用されるのは、地盤がしっかりしている場合に限られます。また、あまり高層の建物を建築する場合にも直接基礎は採用されません。
なお、直接基礎は次のように3つの種類があります。地盤の状態や建築物の種類に応じて適した工法が採用されます。
独立基礎
一言でいうと「柱だけを単独で支える工法」となります。さらに詳しく解説すると、柱の下に独立した基礎コンクリートを入れ、コンクリートの間を梁でつなぐ工法となります。玄関ポーチの柱など、一部分に採用されることはありますが、建築物の全体にこの工法を採用するケースは、最近ではほとんど見られなくなっています。
ベタ基礎
建物のすべての底面に、基礎スラブを構築する基礎工事をベタ基礎と呼びます。大量のコンクリートが必要になるため、コストは割高です。ただ、床一面が鉄筋コンクリートで支えられている状態であるため安定性が高く、この点はベタ基礎のメリットだといえるでしょう。加えて、耐久性にも優れており、シロアリの侵入を防ぎやすいという特徴もあります。布基礎
布基礎は、建物の負荷がかかる部分に鉄筋コンクリートを埋め込む工法です。上述のベタ基礎と異なり、全面にコンクリートを使う必要がないので、コンクリートの使用料を抑えることができます。よって、布基礎のほうがコストを抑えやすくなります。ただ、湿気の影響を受けやすい構造なので、防湿シートなどのアイテムでコーティングする場合も少なくありません。
基礎工事の工程
基礎工事の初めから終わりまでのプロセスは次のとおりです。
- 【1】地縄張り
建物の範囲を表すため、基礎の外周に目印をつけ、建物の範囲を確認します。 - 【2】掘削工事および砕石地業
重機などで、基礎の地盤を掘り返していきます。掘り終えたら、そこに砕石を敷いていきます。これは、地盤の強度をアップさせるために行われます。 - 【3】捨てコンクリート作業
砕石の上に防湿シートを敷きます。そして、外周部に捨てコンクリートを流していきます。 - 【4】配筋
鉄筋を組んでいきます。事前に組み上げられた、いわゆる「ユニット鉄筋」が使われる場合もあります。 - 【5】コンクリートを流す
型枠を組んでコンクリートを流すのですが、枠の両サイドを押すのを忘れないようにします。これは、コンクリートの圧力で枠型が膨らんでしまうのを防ぐために必要です。 - 【6】最後の仕上げ
コンクリートの強度が充分な状態になったら、型枠をはずしてもOKです。また、仕上げとしてつなぎ目などの不要部分を除去したり、土間の打設などの作業をおこないます。
基礎工事に必要な資格
基礎工事に携わるために保有を求められる資格は特にありません。とはいえ、スキルアップを目指したい場合には、やはり関連する資格を取得しておきたいところです。「基礎施工士」「玉掛け技能講習・特別教育」「車両系建設機械運転技能講習」などが基礎工事関連資格の一部です。
まとめ
施工管理技士としては、どのような現場にどのような種類の基礎工事の工法を採用すべきか、といった点についても把握しておくことが大切です。