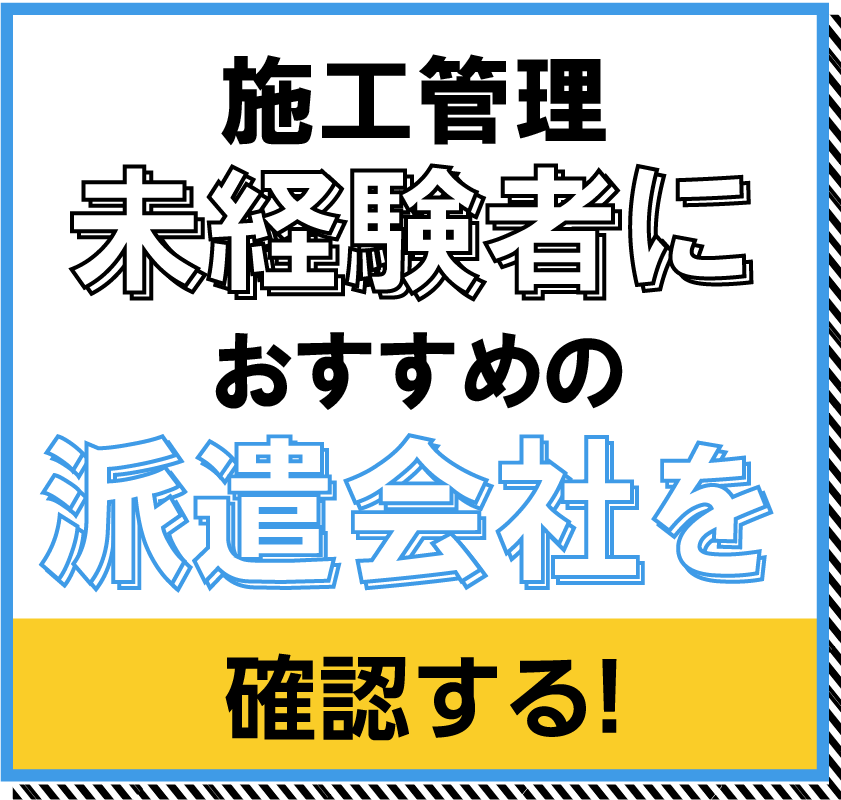ビル設備管理の仕事内容とは?必要な資格についても解説
目指すキャリア別!
施工管理技士の
派遣会社3選
施工管理技士としてのキャリア形成は、単に現場でのスキルを磨くだけではありません。豊富なキャリアの選択肢や専門性の追求、さらには海外での活躍を目指すことも可能です。しかし、どの派遣会社を選ぶかによって、その道が大きく左右されることも事実です。
「多様なプロジェクトを経験してキャリアを広げたい」「専門領域に特化してスキルを深めたい」「海外でチャレンジしてグローバルな視点を養いたい」— それぞれのキャリアニーズに応える派遣会社を厳選してご紹介します。
豊富な選択肢から
自分に合う工種を見出したい
コンストラクション

引用元:オープンアップコンストラクション公式HP
https://openupconstruction.co.jp/contact//
派遣できる工種
建築・土木・電気・プラント
資格支援内容
- 案件の領域バランスが良く、幅広い仕事のマッチングが可能
- 資格取得のサポートがあるので、経験を積みながら手に職を付けることができる
土木の分野で専門性を深めて
キャリア形成をしたい

引用元:カワノ公式HP
https://kawanogroup.com/
派遣できる工種
土木
特徴
- 大手ゼネコン直取引で土木建設業・工事に特化しているため、土木分野のスキルを活かして大型案件にも携われる
- 職場を紹介してくれるので、転勤など働く場所を変えたくない方におすすめ
海外勤務を視野に入れた
経験を積みたい

引用元:レガリス公式HP
https://regalis-gp.com/lp/
派遣できる工種
建築・土木・電気
特徴
- 政府開発援助を含む、海外案件の派遣実績あり
- 電話面接や面接同行のサポートがあるので、面接の成功率を上げたい方におすすめ
ビル設備管理の仕事内容や必要な資格、ビル設備管理で使える施工管理技士資格などについてまとめました。
ビル設備管理とは
ビル設備管理とは、商業ビルやオフィスビルといったビルの電力や空調、機械、防災といった設備を維持管理する仕事のことです。別名ビルメンテナンスとも呼ばれています。
建物にはボイラーや冷凍機、空調機、スプリンクラーなどさまざまな設備があり、法令やオーナーとの契約で点検内容や回数が事細かに決められています。それに合わせてスケジュールを組み点検、保守をします。業務内容は多岐にわたりますが、ビルなどの建築物をいつまでも安全に、快適にかつ長期的に保てるように管理することが大きな役割です。
ビル設備管理の仕事内容
ビル設備管理の主な仕事には、下記のようなものがあります。
- 設備の点検、動作確認
- メンテナンス
- 清掃
- 壊れた設備の修繕
- 日常の施設巡回
また設備に不具合が起きて自身で対応できなかった場合に、専門の工事業者を手配するのも仕事内容のひとつです。工事に立ち会い、工事記録の記入などの作業も行います。施設の多くが24時間体制での管理となっています。そのため勤務はシフト制となり、休日や勤務時間は不規則になりがちです。
ビル設備管理に必要な資格
ビル設備管理を行う上での必須の資格はありません。無資格・未経験の求人もたくさんあって、初心者でも職に就くこと自体は問題ないでしょう。ただし給料が低いところからのスタートになることや、有資格者に比べると採用される可能性が低いことは覚悟しておく必要があります。
やはりビル設備管理の求人では有資格者や経験者を求める方が多く、資格を取っておいた方が就職しやすいのは確かです。管理する施設や設備によって必要な資格は異なるため、一概にこの資格が必要とは言えませんが、設備管理の仕事に需要が高い資格はあります。それがビル管理の基本を押さえた下記の資格になります。これらの資格は、通称「ビルメン4点セット」とも呼ばれています。
- 第二種電気工事士
- 危険物取扱者乙種
- 二級ボイラー技士
- 第三種冷凍機械責任者
これら4つの資格は設備管理を行う上で最低条件のような資格となっているため、ビル設備管理の仕事に就きたいのであれば取得しておいた方がよいでしょう。特に第二種電気工事士は4点の中でも重要とされているので、最初に取得することをおすすめします。
ビル設備管理で使える施工管理技士資格
施工管理の知識がある人は、専門性を買われてビル設備管理会社に入社しやすくなります。実際にビル設備管理会社のホームページを見てみると、各種資格の保有者が公開されていることがあります。その資格の中には施工管理技士資格も含まれており、ビル設備管理業界に施工管理技士の需要があることが分かります。
ビル設備管理で特に需要が高い資格
ビルメン4点セットのさらに上位に位置づけられるものが、下記で紹介する「3種の神器」と呼ばれる資格です。資格取得の難易度は高くなりますがビル設備管理としてのキャリアアップに役立つ資格なので、更に上を目指したい場合は取得しておきましょう。
第三種電気主任技術者
電気主任技術者試験は第三種から第一種に分類されている国家資格で、発電所や変電所、工場やビルなどに設置されている電気設備の保守・監督を行うための資格です。第三種電気主任技術者は、電験三種とも呼ばれています。電気工事士との違いは、電気工事士は工事現場で電気工事を行うための資格であるのに対し、電気主任技術者は保安・監督のための資格であること。電気工事士の方が難易度が低いため、電気工事士試験に合格してから電気主任技術者試験を目指す人も多いです。
第一種~第三種の違いは、扱う対象となる電気工作物の違いです。第三種電気主任技術者は「電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)」を扱えます。
第三種電気主任技術者の試験は理論・電力・機械・法規の4科目あり、試験範囲も膨大です。また、過去に出た問題と同じものはほとんど出題しません。合格率もここ数年は10%を下回るなど、難易度の高い試験です。ただし科目別合格という制度があり、3年間かけて4つの科目に合格すれば第三種電気主任技術者を取得することが可能です。
エネルギー管理士
エネルギー管理士とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」によって定められた国家資格です。「節電」と「エネルギー合理化」のため、エネルギーを使用する設備の維持管理やエネルギー使用量の監視、エネルギー使用効率化、現場指揮などを行います。大規模な工場や施設では、エネルギー管理士員の配置が義務付けられていることが多いです。
エネルギー管理士の試験は、取得前後に1年間の実務経験を設けることで誰でも受験可能です。必須共通科目のほかに、選択科目として熱分野と電気分野から選ぶことができます。2023度の合格率は37%ほど。(※1)
※1参照元:省エネルギーセンター|令和5年度第45回エネルギー管理士試験 合格者発表(https://www.eccj.or.jp/mgr1/test/index.html)
過去問とよく似た問題が出題されやすい傾向があるため、過去問をしっかり演習しておくことが大切です。
建築物環境衛生管理技術者
建築物環境衛生管理技術者は、建築物の維持管理と衛生管理の監督ができる国家資格です。面積が3,000平方メートルを超える特定建築物では建築物環境衛生管理技術者を設置する必要があるため、非常にニーズの高い資格と言えます。
建築物環境衛生管理技術者を受験するためには、一定の実務経験が必要となります。2019年から2021年における合格率は平均17%ほど。簡単な試験ではありませんが、しっかり対策を立てて勉強を積み重ねていけば十分合格を狙えるでしょう。(※2)
※2参照元:「第52回建築物環境衛生管理技術者試験」の合格発表|厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28779.html)