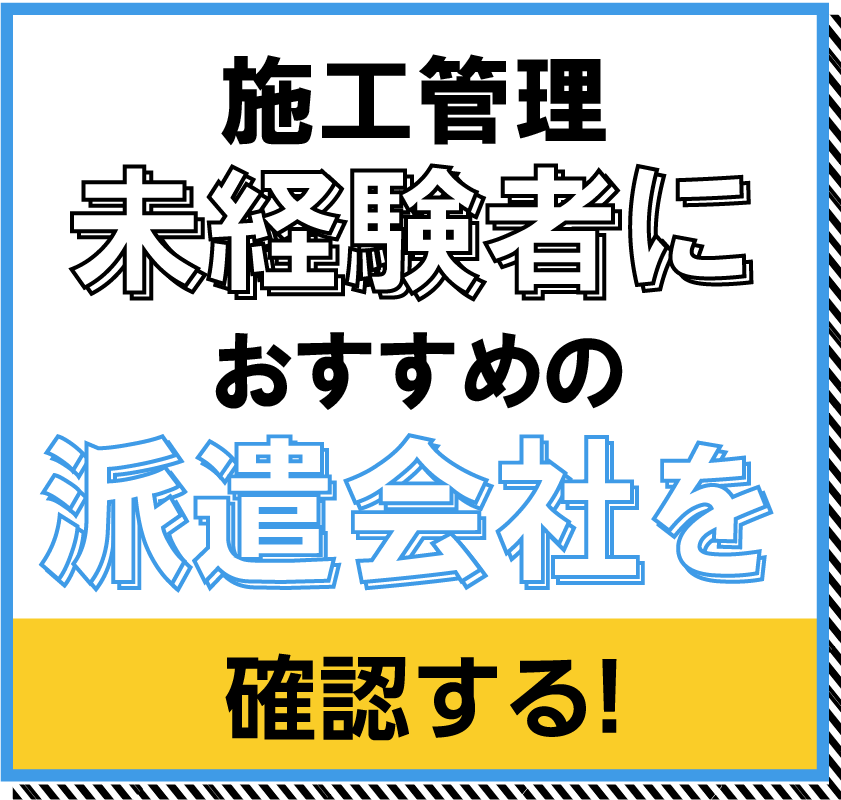施工管理における「安全管理」とは?
目指すキャリア別!
施工管理技士の
派遣会社3選
施工管理技士としてのキャリア形成は、単に現場でのスキルを磨くだけではありません。豊富なキャリアの選択肢や専門性の追求、さらには海外での活躍を目指すことも可能です。しかし、どの派遣会社を選ぶかによって、その道が大きく左右されることも事実です。
「多様なプロジェクトを経験してキャリアを広げたい」「専門領域に特化してスキルを深めたい」「海外でチャレンジしてグローバルな視点を養いたい」— それぞれのキャリアニーズに応える派遣会社を厳選してご紹介します。
豊富な選択肢から
自分に合う工種を見出したい
コンストラクション

引用元:オープンアップコンストラクション公式HP
https://openupconstruction.co.jp/contact//
派遣できる工種
建築・土木・電気・プラント
資格支援内容
- 案件の領域バランスが良く、幅広い仕事のマッチングが可能
- 資格取得のサポートがあるので、経験を積みながら手に職を付けることができる
土木の分野で専門性を深めて
キャリア形成をしたい

引用元:カワノ公式HP
https://kawanogroup.com/
派遣できる工種
土木
特徴
- 大手ゼネコン直取引で土木建設業・工事に特化しているため、土木分野のスキルを活かして大型案件にも携われる
- 職場を紹介してくれるので、転勤など働く場所を変えたくない方におすすめ
海外勤務を視野に入れた
経験を積みたい

引用元:レガリス公式HP
https://regalis-gp.com/lp/
派遣できる工種
建築・土木・電気
特徴
- 政府開発援助を含む、海外案件の派遣実績あり
- 電話面接や面接同行のサポートがあるので、面接の成功率を上げたい方におすすめ
施工管理技士に欠かせない「安全管理」
施工管理技士は、作業現場に関する様々な業務を統括し、指示したり、管理・確認する業務を行っています。そのなかでも「安全管理」は、施工管理技士にとって代表的な業務です。ここでは安全管理の業務について詳しく説明していきます。
安全管理の業務内容は
安全管理の業務内容は、一言で言うと、現場の安全性を確保することです。建築作業などの工事現場には、様々な事故が発生する可能性が潜んでいます。なかには、発生してしまうと取り返しがつかないような事故も。そういった事故を万が一にも起こさせないために、施工管理技士は、現場のリスクを事前に見つけ出し、必要な対策を実施しなければならないのです。
施工管理技士が行う安全管理には、次のようなものが有名です。
- 5S運動(整理整頓を基本にする安全確保の活動)
- KYK(危険予知活動の略語)
- ヒヤリ・ハット運動(事故にはならなかったが危なかった事例の共有)
- 安全大会
工事を無事故で終わらせることは施工管理技士の基本。安全管理は徹底して行わなければなりません。なにより、現場の安全性が確保されなければ、作業を進めることはできないのです。また、工事現場が野外ともなれば、天候や季節によって注意しなければならないリスクは常に変化していきます。安全が確保された作業環境を整えるために、様々な危険性を考慮して、リスクを除去していきましょう。
「安全管理計画書」を作成する
施工管理技士が行う安全管理の基本は、「安全管理計画書」に基づいて実施されます。これは、作業員をはじめとする工事関係者に共有されるもので、事故を防止するために管理者が立案し、責任を持って実行することが、法律において求められています。
安全管理計画書で作成すべき内容は、朝礼や体操に始まり、危険予知活動、作業前に行う作業内容や注意点を作業員全員で確認する「ツールボックスミーティング」、安全器具の点検、安全確認のための巡回や是正活動、また終業前の清掃まで、漏れがないように行います。また、特別なリスクが作業にあたる作業員には、別途で安全管理を実施します。
資材や工法の確認
施工管理技士は、現場で使われる機材や資材の点検を行います。それらが安全上問題なく使用できるかどうか、チェックしなければなりません。また、その現場で実施される工事方法が定められた通りの内容になっているかどうかも、安全性を管理する上で重要なポイントです。
工法の確認をしっかりと行うことで、過去に行われた同じ工法において危険だった工程をチェックできたり、施工の難易度を知ることができます。過去の事例をしっかりと踏まえた安全管理を行うのです。
天候に対する安全管理
おうおうにして天候によって進捗が左右される現場作業は、台風や強風といった自然現象に対応した安全管理の対策を行うことが求められます。
例えば、強風の際に注意しなければならないのが、建材や資材の飛散対策です。夏になれば作業現場が高温になるため、作業員の熱中症を想定して、水分を補給する指示を出してあげたり、休憩時間を多めにとれるように調整しなければなりません。
作業員の安全意識を向上させる
工事現場で発生する事故は、作業員の油断をはじめ、心理的な原因によって起こるものが少なくありません。そこで施工管理技士は、作業員の安全意識を向上させる取り組みを実施することも欠かさず行う必要があります。
安全意識を高めるには、危険に対する認識を作業員に持ってもらえるように、安全点検の時間をしっかりと設けたり、事故に対するミーティングを行うことが効果的です。
作業員や現場で繰り返し言葉にできるように、安全スローガンをつくることもよいでしょう。スローガンは、注意すべき対象が明確になり、仕事のなかで意識しやすくなるように、具体的なものにしましょう。
コミュニケーションを頻繁に取る
工事現場は、施工業者の作業員はもちろん、現場に初めて入る新人やベテランの職人さんなども出入りする場所です。そのため、コミュニケーション不足になってしまいがち。しかし、コミュニケーションがあまり行われていない現場では、不要な緊張感や人間関係で齟齬が生じてしまい、業務にも悪影響が出てしまいます。そのなかには、事故の発生という可能性もあるのです。
施工管理技士は、現場で働く様々な立場の作業員のあいだに立って、コミュニケーションを円滑にとれるような雰囲気作りをおこなう役割もあります。これもまた、施工管理技士が行う安全管理の業務になります。
安全管理に必要なスキルは?
施工管理技士が安全管理を行う際、必要になるスキルにはどのようなものがあるでしょうか?
コミュニケーション能力
安全管理の業務で重要と言えるものが、施工管理技士のコミュニケーション能力です。作業員や職人さんと意思疎通を図り、現場に物的・人的な異常が起こる危険性を察知することが、安全管理では欠かせないからです。
例えば、挨拶や簡単な会話からでも、作業員の健康チェックができますし、何らかのストレスやトラブルを抱えていないか、チェックすることができます。モチベーションや集中力が低い状態では、事故も発生しやすいため、施工管理技士は緊密にコミュニケーションを図っていかなければなりません。
リスクを察知できる注意力
これは経験の量でも変わってきますが、安全管理で重要な能力として、リスクを察知できる注意力もあげなければなりません。常に、「目の前の現場に危険があるかもしれない」という視点を持ち続けながら、機材や現場作業のチェックをしていきましょう。
ヒヤリハット事例の紹介
最後に、現場におけるヒヤリハット事例を紹介します。
建材の飛び出し部分
工事現場で特に多いのが、建材などが外部へと飛び出しており、その飛び出し部分が作業員に接触してしまう、という事例です。「仕上げの建材を先に取り付けるようにする」、「安全ネットでしっかりと飛び出し部分を覆う」といった安全確保を行うようにしましょう。
落下物
また、作業現場では頭上からの落下物による事故も頻繁に起こっています。建設現場をはじめ、工事現場では落下事案をゼロにすることは非常に難しいため、仮に上から何かが落下してしまうミスが発生しても労災事故が発生しないように、上下で同じタイミングで作業をしない、といった業務計画を徹底しましょう。
転落事故
誰もが「こんなわかりやすいところから転落することはないだろう」と思う場所でも、作業をしていて手元に気を取られていたり、疲労がたまっているといった状態になれば、転落事故が発生してしまうものです。初心者はもちろん、ベテランの職人であっても転落事故を起こしてしまうもの。床などに開口部分がないように現場管理を行ったり、どうしても開口部ができる現場ではその上にフタを設置する、といった安全対策を行いましょう。