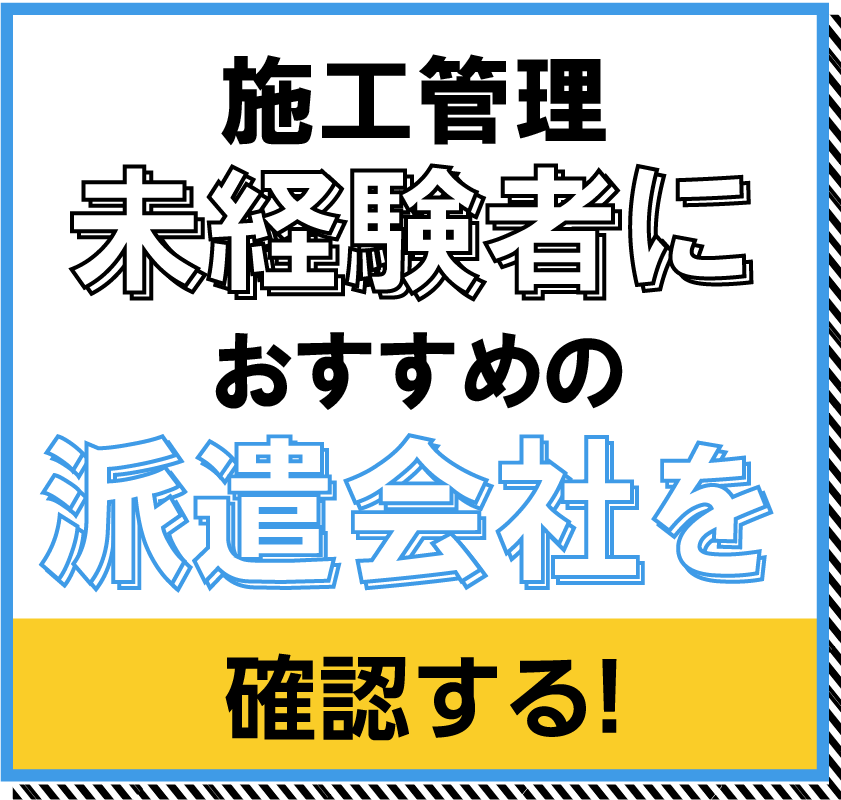「施工計画」とはどのようなもの?
目指すキャリア別!
施工管理技士の
派遣会社3選
施工管理技士としてのキャリア形成は、単に現場でのスキルを磨くだけではありません。豊富なキャリアの選択肢や専門性の追求、さらには海外での活躍を目指すことも可能です。しかし、どの派遣会社を選ぶかによって、その道が大きく左右されることも事実です。
「多様なプロジェクトを経験してキャリアを広げたい」「専門領域に特化してスキルを深めたい」「海外でチャレンジしてグローバルな視点を養いたい」— それぞれのキャリアニーズに応える派遣会社を厳選してご紹介します。
豊富な選択肢から
自分に合う工種を見出したい
コンストラクション

引用元:オープンアップコンストラクション公式HP
https://openupconstruction.co.jp/contact//
派遣できる工種
建築・土木・電気・プラント
資格支援内容
- 案件の領域バランスが良く、幅広い仕事のマッチングが可能
- 資格取得のサポートがあるので、経験を積みながら手に職を付けることができる
土木の分野で専門性を深めて
キャリア形成をしたい

引用元:カワノ公式HP
https://kawanogroup.com/
派遣できる工種
土木
特徴
- 大手ゼネコン直取引で土木建設業・工事に特化しているため、土木分野のスキルを活かして大型案件にも携われる
- 職場を紹介してくれるので、転勤など働く場所を変えたくない方におすすめ
海外勤務を視野に入れた
経験を積みたい

引用元:レガリス公式HP
https://regalis-gp.com/lp/
派遣できる工種
建築・土木・電気
特徴
- 政府開発援助を含む、海外案件の派遣実績あり
- 電話面接や面接同行のサポートがあるので、面接の成功率を上げたい方におすすめ
工事全般を管理する計画書
施工管理技士が行う管理業務は、すべて「施工計画」に基づいて管理されています。施工計画とは、一言で説明すれば、現場の作業が、設計書や仕様書通りに、定められた予算内で、求められる安全性を確保しながら行われるために、すべての工法を計画することです。だからこそ、施工管理技士の管理業務において施工計画は、工事のすべてに関わる極めて重要なもの、と言っても過言ではないのです。
施工管理技士は、工事現場の管理業務全般を監督する役割を担い、予算(原価)、工程、品質、安全性、資材や機材、作業員の手配など、管理しなければならない対象は非常に多岐に渡り、作業に漏れがなく、効率よく管理することが求められます。
また、施工計画書は建設工事を進めるために必要なだけではなく、発注先に提出することも求められます。とりわけ公共事業に携わる案件では、細かい規程に従いながら施工計画書を作成しなければなりません。内容に不備がある場合には、提出先から修正を依頼されて差し戻される、いわゆる「手戻り」にもなってしまい、工事の進捗に影響を与えてしまいます。反対に、施工計画書を不備なく作成でき、安全管理や地域貢献性を盛り込むことができれば、信頼を得ることもできるのです。
施工計画の策定内容は?
建設工事を計画通りに進めるために、施工計画のなかで策定しなければならない内容は、どのようなものが見ていきましょう。
施工計画書を作成するにあたって検討しなければならないものは、大きく分けて以下の項目が挙げれられます。
- 建設工事の概要
- 計画工程表
- 現場組織表
- 指定機械
- 主要船舶・機械
- 主要資材
- 施工方法
- 施工管理計画
- 安全管理
- 緊急時の体制および対応
- 環境対策
- 現場作業環境の整備
- 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
- その他
上記のように、様々な項目で十分に調査・検討を行うことが、施工計画には欠かせません。適切な施工計画を立案して、現場の施工体制を適切に決めるためには、施工に関わる経済性や安全性も忘れずに確認する必要があります。策定すべき事柄に抜けや不備があれば、実際の現場作業の進捗や品質にも影響してしまいます。それほどまでに、施工計画は重要なものなのです。
進捗率に関わる施工計画
施工計画を立案し、作業中も把握できているかどうかは、現場作業の進捗にも関わります。
施工計画では、現場工事における種別や製品規格、数量などが細かく定めます。作業をスムーズに監督していくためにも策定した施工管理技士が内容をきちんと理解し把握する必要があります。現場で作業員に資材などについて質問されたとき、施工管理技士がその場で答えられるか、それとも事務所に戻って計画書を確認しなければならないかで、作業の進捗は変わります。
施工管理技士として優秀と呼ばれる人たちは、施工計画を抜かりなく策定し、工事中もつねに頭にインプットして監督業務にあたります。工事が進捗するにつれ、次の工程で必要な資材や機材の手配を滞りなく行うこと、トラブルが発生すればフォローの対策を構えていたりと、常に先手を打つことができます。もちろん経験を積むことで、場面に合わせた対応を取ることができるようになるでしょう。しかし、そうした先を見据えた対応というのも元をたどれば施工計画をしっかりと立てるように心掛けていることがスタートになっていると言えるでしょう。
施工計画のポイントは?
ここからは施工計画ではどのようなポイントを押さえて策定するのかを確認してみましょう。
工事の趣旨を明確にする
施工計画書では、工法や工期など、要点となる必要項目を明確に記載しておくことが重要です。内容が不明確だったり、意図が伝わらない記載の仕方をしてしまうと、計画書の「手戻り」が発生してしまいます。誰が目にしても分かりやすい計画書にすることがポイントです。
明確で分かりやすい施工計画書にするためには、いわゆる「5W1H」(誰が、いつ、どこで、どのような工法で、なぜ、どのような資材・機材で)を押さえて作成することが欠かせません。それぞれの作業について、これらの要点を押さえておけば、実際の工事にあたっても誤りなく遂行されることでしょう。
反対に、「5W1H」が押さえられていない計画書では、作業の抜けややり直しが発生してしまいかねません。現場作業の進捗にも関わってきますので、施工計画はわかりやすいものにしましょう。
現地調査は綿密に
施工計画は、建設工事が実際に行われることになる現場の調査をしっかりと行い、現場環境を計画に反映することが重要です。
建設工事では、これから建設する建設物も、それを建てる現場環境も、毎回ごとに異なりますから、施工計画もすべて、いわばオーダーメイドで立案しなければなりません。建築物はもちろん、工事現場の立地条件や自然環境などを調査しなければ、計画を策定することができないのです。
現場調査を行うことによってはじめて、見えていなかったリスクや見積もりに入れていなかったコストなども洗い出すことができます。こういった調査がもしも不十分であれば、工事現場の作業や工程の進捗のトラブルの原因になります。
事前調査は、複数回に渡って実施したり、複数人でチェックすることで、より正確に行うこともできます。
実現困難な内容は入れない
施工計画の立案では、安全管理や地域貢献などを盛り込むこともあります。これは、公共事業などの場合、工事成績の評定点数に好影響を与えるからです。しかし、いくら好印象を与えたいからと言って、実現困難な内容を施工計画に入れてしまうと、現場の作業が圧迫されたり、実現できなかったことを指摘され、マイナスになってしまう可能性があります。
施工管理技士であれば、地域貢献などのイメージアップ要素も計画に入れて、より良い点数を獲得したい心理がありますが、点数を求めすぎるあまり、現場の作業員に負担がかかってしまうと本末転倒です。イメージアップの提案のなかには、実際に行うとコストがかかりすぎてしまうものもあります。せっかく工事を完遂しても、利益が減ってしまうことは問題ですよね。実現困難な内容は施工計画に入れないように、よく考えましょう。
初心者はテンプレートを上手に使う
最近では、初心者でも作成することができる施工管理計画書のテンプレートを、簡単に手に入れることができます。建設、土木はもちろん、機械工事や電気設備工事など、工事内容によって使い分けることができる様々なタイプの施工計画書のテンプレートが準備されています。テンプレートには、施工計画で必要な項目などもあらかじめ記載してくれているため、計画書の作成に慣れていない初心者でも抜かりなく手を付けることができます。
発注者からの手戻りも防ぐことができますので、ぜひ活用してみてください。
施工計画書には何を盛り込めばいい?
上記のようにポイントを押さえた施工計画を策定すれば、今度は施工計画書の細かい記載に移ります。
施工計画書は、施工管理技士や発注者はもちろん、工事に関わる施工業者など、様々な関係者が共有して、現場の作業を計画通り進めることができるように作成されるものです。分かりやすいように、要点を押さえて計画することがもちろん、基本的な内容から具体的に作業に欠かせない情報まで、もれなく記載しなければなりません。
例えば、まず最初に記載すべき内容である「工事の概要」では、工事の目的や意図が理解されなければなりませんし、どのような工程で進めることが計画されているのか、現場の組織体制や施工体制はどのようになっているのか、安全性を確保するために必要な情報、資材や機材として指定されているものは何か、施工方法はどのようなものか、品質管理に必要な写真やチェック項目はなにか、トラブルがあった場合の緊急時の対応策、周辺の環境対策など、枚挙にいとまがないほど。それぞれの現場で記載すべき内容をきちんと考慮して、抜けなく作成しましょう。
施工計画書を手軽に作成するテクニック
施工管理計画書は、非常に重要ながら、作成には手間がかかるものです。だからこそ、すこしでも手軽に作成するテクニックを使って、効率的に作成しなければなりません。近年では、施工管理計画書をパソコンで作ることが当たり前になっていますが、使用するソフトは、テンプテートが使いやすいエクセルはもちろん、施工管理計画書を作成するための専用ソフトにも、様々な種類があります。
フリーのテンプレートを使用するのであれば、「日本建設業連合会(日建連)」が提供している施工管理計画書のエクセルデータが便利です。作成の手間をできるだけ軽減できるように、様々な工事の種類にあわせてデータが用意されていますし、細かい工事の内容にあわせて、書類の内容を変更できるようになっています。使用するエリアの汎用性も高く、全国のどの地域でも対応できます。「公共建築工事標準仕様書(2016年度版)」に準じたものなので安心ですね。
エクセルデータの他にも、1989年にリリースされた「施工計画書作成支援システム」は、全国で3万社以上の導入実績がある優れもの。イラスト付きのテンプレートで施工管理計画書を手軽に作成できるほか、設計の変更も自動で行ってくれます。工事の成績評定を考慮した計画書の作成もできますから、施工管理技士の強い味方です。「NETIS(新技術情報提供システム)」にも対応しているため、加点評価の対象にもなっています。