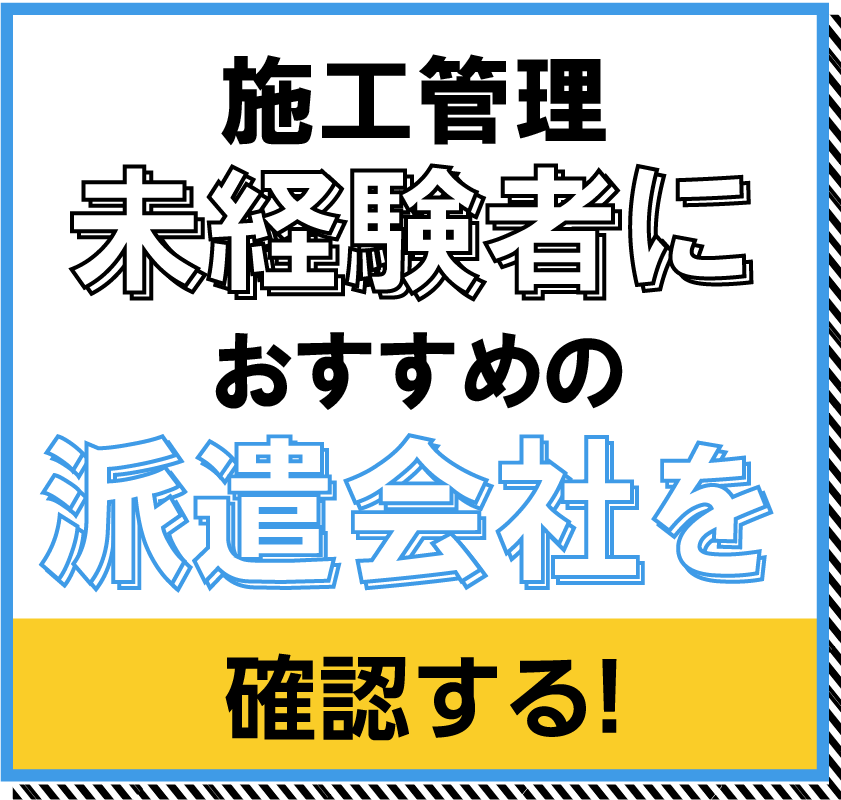施工管理技士が知っておきたいヒヤリハット事例
目指すキャリア別!
施工管理技士の
派遣会社3選
施工管理技士としてのキャリア形成は、単に現場でのスキルを磨くだけではありません。豊富なキャリアの選択肢や専門性の追求、さらには海外での活躍を目指すことも可能です。しかし、どの派遣会社を選ぶかによって、その道が大きく左右されることも事実です。
「多様なプロジェクトを経験してキャリアを広げたい」「専門領域に特化してスキルを深めたい」「海外でチャレンジしてグローバルな視点を養いたい」— それぞれのキャリアニーズに応える派遣会社を厳選してご紹介します。
豊富な選択肢から
自分に合う工種を見出したい
コンストラクション

引用元:オープンアップコンストラクション公式HP
https://openupconstruction.co.jp/contact//
派遣できる工種
建築・土木・電気・プラント
資格支援内容
- 案件の領域バランスが良く、幅広い仕事のマッチングが可能
- 資格取得のサポートがあるので、経験を積みながら手に職を付けることができる
土木の分野で専門性を深めて
キャリア形成をしたい

引用元:カワノ公式HP
https://kawanogroup.com/
派遣できる工種
土木
特徴
- 大手ゼネコン直取引で土木建設業・工事に特化しているため、土木分野のスキルを活かして大型案件にも携われる
- 職場を紹介してくれるので、転勤など働く場所を変えたくない方におすすめ
海外勤務を視野に入れた
経験を積みたい

引用元:レガリス公式HP
https://regalis-gp.com/lp/
派遣できる工種
建築・土木・電気
特徴
- 政府開発援助を含む、海外案件の派遣実績あり
- 電話面接や面接同行のサポートがあるので、面接の成功率を上げたい方におすすめ
建設現場では一歩間違えると事故につながる「ヒヤリハット」が発生することも多くあります。ヒヤリハットが起きたとき、事故にならなくてよかった…と思うだけではなく、原因を分析して対策を講じることが大切です。ここではヒヤリハットの説明や報告書の目的、施工管理技士が知っておきたいヒヤリハット事例について紹介します。
ヒヤリハットとは
ヒヤリハットとは、危ないことが起きたけれど幸い災害や事故には至らなかった事象のこと。結果として重大な事象にはならなかったものの、一歩間違えたら事故になっていた可能性がある出来事が該当します。
ヒヤリハットは、語感から想像できるとおり「ヒヤリとした・ハッとした」という意味のことばです。建設現場では、このヒヤリハットが起こりやすいです。事故を防止するためにはヒヤリハットをそのままにするのではなく、教訓として改善策を立て、実行することが大切です。
ヒヤリハット報告書の目的とは
建設現場で実際に起こった危険な事例をまとめた「ヒヤリハット報告書」というものがあります。ヒヤリハット報告書の目的は、ヒヤリハットの再発防止と労働災害を事前に防ぐこと。ヒヤリハット体験を収集、根本的な原因を分析し、活用することで、同様の事例が起こらないように適切な安全対策を講じることが可能になります。またヒヤリハットをスタッフ全員で共有することで、現場の安全意識がより高まるでしょう。
ただし、ヒヤリハット事例を収集するのは簡単ではありません。色々指摘されるのが面倒で報告しない人もいますし、自身の評価が低くなることを恐れて報告しない人もいることでしょう。まずはヒヤリハットが報告しやすいような現場の雰囲気づくりを行う必要があります。また、報告した方が有利になる制度作りや、報告書を簡単に作成・提出できるシステムづくりが求められます。
ヒヤリハット報告書の書き方
状況を記載
ヒヤリハット報告書には、発生した日時や場所、作業内容、実際に起きたときの状況を詳細に記載する必要があります。また、当時の疲労感や眠気などの心身状況も記載しておくとよいでしょう。
大切なことは、ヒヤリハットに至るまでの状況を克明に記載することです。「〇〇の作業中にヒヤリハットのきっかけが起きて、△△になりそうになった」のような流れで書くと分かりやすいです。
原因・予防策を記載
ヒヤリハットが起きた原因と、もし事故に発展していた場合に想定される最悪な事態についても記載します。原因の追及や分析は管理者が行いますが、当事者としてどのように捉えているのかを書くことが大切です。自身の不注意だったのか、現場の環境に不備があったのか…など当時を振り返り、原因についてよく考えてみましょう。
また想定できる予防策や再発防止に対する現場への要望もあるなら、それらもしっかり記載しましょう。今後どう対処すれば安全対策が高まるか、当事者の立場から記載するとよいです。
建設現場におけるヒヤリハット事例
建設現場で実際に起こったヒヤリハットの事例について紹介します。さまざまな事例がありますが、どの事例も一歩間違えたら大事故につながる危険なものばかりです。
転落
建物の壁面にはしごを立てかけて作業しているときに、転落しそうになったという事例があります。はしごはしっかりと固定されていませんでした。
また、鉄骨の梁の上でレベル測定中に足が滑って墜落しそうになった、足場の階段を降りるときに手すりがなかったため足を踏み外して滑り落ちそうになったなどの事例も存在します。
飛来
ボイラーでの灰出し作業中に誤ってパイプレンチや接続用L型パイプなどを落とし、危うく他の作業員に当たりそうになった事例があります。また、クレーンで鋼材をトラックの荷台に移す際にワイヤーが切れて落下したり、枠型の制作時に作成済みの枠型が突風にあおられ15mほど移動した事例も。
飛来は作業員だけでなく、通行人にも被害を及ぼす可能性があります。
感電・火災
配電盤の配線変え作業の際、ビズが落下して取り出そうとしたら主電源スイッチの一次側に腕が触れそうになった事例があります。もし触れていたら感電していました。
また、廃油貯蔵タンク内の固形分を鉄製のスコップで掃除していたところ、タンク内壁とスコップの間に衝撃火花が出たのに気が付いたという報告もあります。このときは、直ちに衝撃火花が出ない材質のスコップに切り替えて事なきを得たとのことです。
接触
有害物との接触は目に見えない怖さがあります。例えば、装置を有害成分を含む洗浄液で洗っていたところ、外部から入ってきた作業員に匂いについて指摘されて慌てて換気して事故を免れた事例が発生しています。
また、廃液処理場のバルブ操作用地下ピットで作業員が倒れているのを発見。慌てて救助しに中に入ろうとして、他の作業員に止められて二次被害を免れたという例もあります。
崩壊・倒壊
建設現場で起こる崩壊・倒壊は、多くの作業員を巻き込む大事故に発展しかねません。ヒヤリハット事例としては、作業中に地山が崩壊したので慌てて逃げたケースや、立てかけていた木材が突然倒れてきて身体に当たりそうになったケースなどが報告されています。
挟まれ・巻き込まれ
トラック誘導していたとき電信柱とトラックの間に危うく挟まれそうになった事例や、バックホー誘導作業中に後進したバックホーに轢かれそうになったという事例があります。
また、小型チェーンソーで作業中、首に巻いていたタオルが垂れ下がりチェーンソーに巻き込まれそうになったという事例も。少しの油断でヒヤリハットは発生してしまいます。
転倒・激突
段ボールを両手に抱えて運搬していたところ、通路に放置されていたパイプに躓き転倒しかけた事例が出ています。
また、ダンプトラックで土を運んでいて、土を下ろそうと一旦車を止めてからバックしかかったところで、バックミラーに人が見えて慌ててブレーキを踏んで事なきを得たという報告もあります。
ヒヤリハット対策
日頃の注意喚起
ヒヤリハット対策として、日頃の注意喚起が大切です。ヒヤリハットが発生する前に作業グループで話し合い事前に対策を立てる危険予知活動を行ったり、新規作業員への教育を徹底するようにしましょう。
作業員や重機は入れ替わりも激しいです。そのため特別な機会だけ注意喚起をするのではなく、常日頃から行うことが必要となります。
安全な作業環境の整備
安全な作業環境の整備を行うことが求められます。柵やネット・ロープなどを設置することで、転落・墜落対策となります。また、安全を確保できる作業床を設けることも必要ですし、作業員が安全帯をつけることは必須です。
保護具の着用
服装を正しく着用することは、ヒヤリハット対策の基本です。袖口のボタンは留め、ズボンの裾は長靴に入れるようにしましょう。
また、作業内容によっては保護具の着用が定められています。ヘルメットはあご紐をしっかりと止めましょう。アーク溶接・防振の際には、専用の手袋を付けます。また粉じん作業を行うときには粉じん作業メガネが、有害光線には遮光眼鏡が必要となります。
機械の点検・メンテナンス
機械の点検やメンテナンスは、挟まれ・巻き込まれ・激突事故の防止に繋がります。建設機械は特定・定期点検が法によって定められています。異常が見つかった場合は、すぐに補修や交換を行うようにしましょう。また異常が見つからなかった場合でも、実施した点検・メンテナンス内容は記録しておくことが大切です。
作業員の健康管理
作業員の健康管理を行うことも大切です。事故や災害はヒューマンエラーによって発生することも多いもの。危険軽視や不注意、疲労による注意散漫などが原因で起こります。
ヒューマンエラーをゼロにすることは難しいですが、日頃から健康管理に気を付けることで少しでも減らすことはできるでしょう。
まとめ
建設現場では多くのヒヤリハット事例が発生しています。再発防止のために大切なことは、ヒヤリハット事例を収集し、分析すること。そして有効な対応策を講じることです。常日頃から注意喚起を行い、安全な現場づくりに努めましょう。