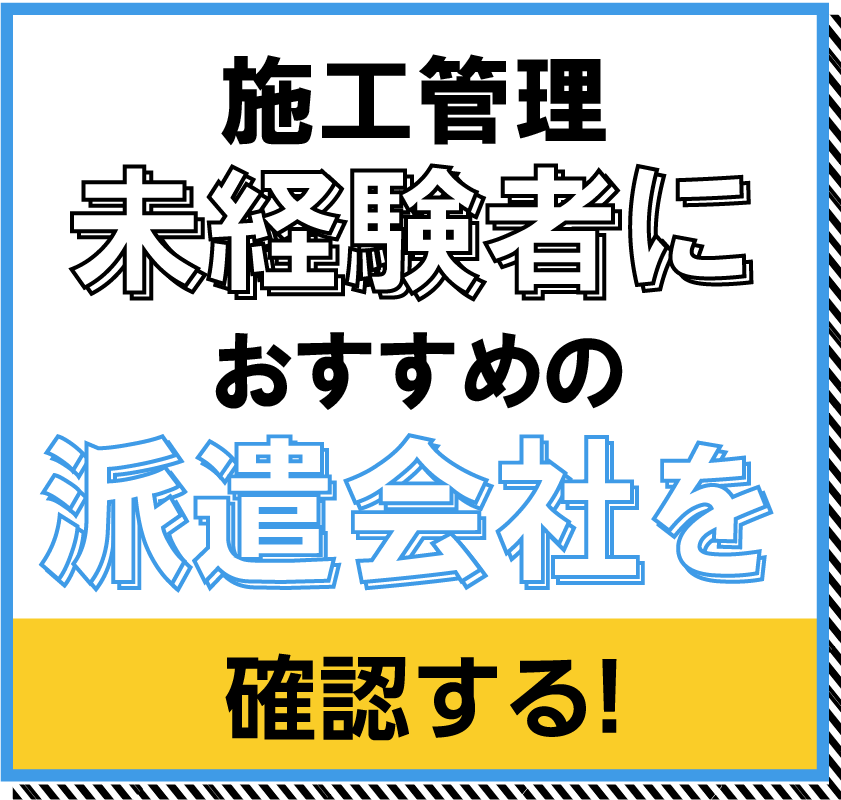施工管理技士は休みないの?
目指すキャリア別!
施工管理技士の
派遣会社3選
施工管理技士としてのキャリア形成は、単に現場でのスキルを磨くだけではありません。豊富なキャリアの選択肢や専門性の追求、さらには海外での活躍を目指すことも可能です。しかし、どの派遣会社を選ぶかによって、その道が大きく左右されることも事実です。
「多様なプロジェクトを経験してキャリアを広げたい」「専門領域に特化してスキルを深めたい」「海外でチャレンジしてグローバルな視点を養いたい」— それぞれのキャリアニーズに応える派遣会社を厳選してご紹介します。
豊富な選択肢から
自分に合う工種を見出したい
コンストラクション

引用元:オープンアップコンストラクション公式HP
https://openupconstruction.co.jp/contact//
派遣できる工種
建築・土木・電気・プラント
資格支援内容
- 案件の領域バランスが良く、幅広い仕事のマッチングが可能
- 資格取得のサポートがあるので、経験を積みながら手に職を付けることができる
土木の分野で専門性を深めて
キャリア形成をしたい

引用元:カワノ公式HP
https://kawanogroup.com/
派遣できる工種
土木
特徴
- 大手ゼネコン直取引で土木建設業・工事に特化しているため、土木分野のスキルを活かして大型案件にも携われる
- 職場を紹介してくれるので、転勤など働く場所を変えたくない方におすすめ
海外勤務を視野に入れた
経験を積みたい

引用元:レガリス公式HP
https://regalis-gp.com/lp/
派遣できる工種
建築・土木・電気
特徴
- 政府開発援助を含む、海外案件の派遣実績あり
- 電話面接や面接同行のサポートがあるので、面接の成功率を上げたい方におすすめ
施工管理の仕事に休みはないのか?
「激務」「休めない」といったイメージを持たれがちな建設業界。実際に、「建設業界においては、半数を超える約65%の人が週休1日で就業している」※というデータも存在しています。これでは、ブラックな印象を持たれてしまうのも致し方ないと言えるかもしれません。
そんな建設業界のなかでも、とりわけ過酷とされるのが施工管理技士というポジション。経験者のなかには、「施工管理の仕事はやめておけ」と進言する人もいるほどです。
一体、なぜこのような過酷な状況がまかり通っているのでしょうか。考えられる2つの原因について、詳しく見てみましょう。
※参照元:(PDF)国土交通省「建設業における働き方改革」 (https://www.mlit.go.jp/common/001189945.pdf)
時期によって休日数が変動する?
繁忙期と閑散期で月間3日の差がある
施工管理の休みや休日数に関する問題として、そもそも繁忙期と閑散期では仕事のスケジューリングが大きく変わってしまい、工事の進捗や工期といった条件によっては月間3日の差が生じるといったケースもあります。
そもそも施工管理の仕事は一般的な会社員の平均休日数よりも少ないといわれる中、繁忙期でさらに休日が減少していくと、いよいよ十分な休みを確保できずにストレスや疲労が蓄積する原因にもなるでしょう。
繁忙期は月4回以下になるケースも
繁忙期における施工管理技士の働き方や勤務形態については、月の休日数が5日や4日を下回るケースさえ存在するとされています。仮に1ヶ月に土日が5回あるとして、休日数が4日未満となれば、現実的に週1回の休みさえ確保されていないこともあり得る状態になってしまいます。
もちろん実際の休日数は企業や現場によっても異なりますが、繁忙期の施工管理の仕事では休日を確保することは難しくなりやすいという点は全国的に共通の課題であるようです。
「土日祝休み」の会社も少なくない
建設業界や施工管理技士の深刻な労働環境に加えて、少子高齢化による人材不足と労働力の減少を改善するため、政府や民間団体などが一丸となって建設業界の働き方の是正に取り組んでいることも事実です。
そのため、近年は少しでも採用活動を強化して人材の拡充を図ろうと、福利厚生に配慮したりきちんと休日を確保したりしている企業が増えていることも見逃せません。
今後はさらに土日祝日が休みの会社やワークライフバランスに配慮した会社が増えていく可能性もあります。
休みが少ない原因
工期を優先
施工の現場には、当然ながら工期が存在します。施工管理者は工期に間に合うようにスケジュールを組み、作業の管理を行うこととなりますが、現場にはトラブルがつきもの。資材到着の遅延、設計ミスの発覚、あるいは近隣からのクレームといった問題から、スケジュールにずれが生じてしまうことも珍しくありません。
こうなると、管理者はそれぞれのトラブルに対応しつつ、改めて工事計画の見直しを行わなければなりません。遅れをカバーするために残業する、休日返上で現場に出るといった行為は、業界全体でしばしば行われているのが実情です。
人が足りない…
かねてより、建設業界は人手不足にあえいでいます。なかでも、特に深刻なのが施工管理技士の不足。有資格者の高齢化による引退や他業種へのキャリアチェンジにより、人手不足は加速する一方だと言われています。
有資格者全体の人数が減れば、施工管理技士一人あたりにのしかかる業務の量はどんどん多くなります。そのため、現役の技士は働き詰めの毎日を強いられることになりがち。その結果、忙しすぎる職場に見切りをつける若手技士が続出し、ますます人手不足のスパイラルが加速してしまうというわけです。
施工管理技士の生の声
一日中仕事で寝る間が無い日もあった
(前略)3年目から東京支店の施工管理部に配属となった私は、これまで以上に仕事に割く時間が多くなりました。ほぼ毎日残業し、帰宅しては寝るだけの生活を送っていました。また職種柄、夜間対応もしなければいけないため、昼も夜も働き寝る時間がないこともありました。(後略)
引用元:エリートネットワーク(https://www.elite-network.co.jp/voice/entry-77456.html)
日付が変わってから帰宅するのも当たり前
(前略)現場の作業自体は、7:00から16:00なので、作業員は16:00になると「お疲れ様っす」と言って帰って行きますが、施工管理はそこからが本番。「定時」が過ぎてから事務所に戻り、次の日のための段取りや記録のために撮影した写真のチェック、書類の作成などを行います。
これで20:00に帰れればいい方ですが、日付が変わってから帰ることや、朝は日の出前に出勤することもしばしば。休みはお情けで日曜だけ休ませてもらっているような状態でした。(後略)
引用元:みんなのブラック企業通信簿(https://jobissue.net/experiences0102/)
改善の方向には向かっている
「働き方改革」の波
2019年現在、国を挙げて推進されている「働き方改革」。建設業界も例外ではなく、過酷な現状を打破するための施策が少しずつ打ち出されています。福利厚生の見直しや給与のアップはもちろんのこと、長時間労働の是正や年間休日数の増加など、ワークライフバランスの改善に取り組んでいる企業が増えてきているのです。
こうした企業に勤める施工管理技士からは、「残業や休日出勤をすると、むしろ注意されることが増えた」「休日出勤をしたら、必ず振替休日を取れるようになった」といった声も挙がっています。
休める会社か否かを見極めよう
先述のとおり、建設業界全体の風向きは少しずつ良い方向に変わってきています。しかし、一部の企業では、未だに「週休1日」「毎日の残業」といった過酷な勤務体制が横行しているのも事実。激務によって心身に過剰な負担をかけないためには、あらかじめ「きちんと休める会社かどうか」を慎重に見極めることが大切です。
具体的には、「設計から施工、引き渡しまでの一連の流れを全て自社で行っているかどうか」「職人と施工管理者のコミュニケーションが良好かどうか」といった点に注目してみましょう。設計を外注していたり、職人と管理者がきちんと連携できていなかったりすると、トラブル発生による工期の遅れが起こりやすくなり、結果として休みが減ってしまう可能性があるためです。